このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
企業がカーボンニュートラルを推進するにあたっては、まずCO2排出量の把握に取り組む必要があります。しかし、本格的に脱炭素化を進めるためにはサプライチェーン全体で段階的に把握することが大切です。ここでは、CO2排出量の算出方法をご紹介します。
中小企業は、自社だけで責任を持って削減できるScope1・2のみの算定にとどめる場合もあります。しかし、Scope3を含む算定を行うことで、サプライチェーン全体の排出量を把握できて削減箇所の明確化ができる、取引先との関係を強化できる、資金調達しやすくなるなど、多くのメリットがあります。
環境省では、サプライチェーンをScopeとして区分し、CO2排出量を算出するガイドラインを策定しています。
カーボンニュートラルにおけるScopeは、サプライチェーンでのCO2排出量の算定範囲を区分したものです。Scope1~3まであり、それぞれ以下のように定義されています。
環境省は、サプライチェーンのCO2排出をこれらに分け、CO2排出量の算出方法を細かく規定しています。
参照元:【PDF】環境省 サプライチェーン排出量 概要資料 (https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/SC_gaiyou_20230301.pdf)
自社による直接的なCO2排出に該当するScope1は、「活動量×排出係数」の計算式でCO2排出量を算出可能です。排出係数は使用した燃料・エネルギーによって異なるため、まずは燃料ごとの排出係数をチェックしてみましょう。
なお、Scope1は以下のような活動が当てはまります。(代表的な例です)
参照元:【PDF】環境省公式HP(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran_2023_rev4.pdf)
Scope2は、「活動量×排出係数」でCO2排出量を算出可能です。排出係数はエネルギー供給元によって変わります。
電気などエネルギー供給事業者によって排出係数を使い分ける必要があります。
Scope1・2のいずれにも当てはまらない間接排出のScope3は、「活動量×排出係数」でCO2排出量を算出するのが基本です。ただし、Scope3はカテゴリによって区分されているため、カテゴリ別に算出するなど複雑で、専門家の支援を受けて算定していくのが一般的です。
カテゴリは以下の15種類に区分されています。
Scope3は自社以外の上流・下流における排出量であり、自社が保有している情報のみで簡易に算出する方法や上流および下流のサプライチェーンの各事業者から情報を得て算出する方法などがあります。より精度の高い排出量を算出する場合、サプライチェーンの各事業者に情報提供を依頼しなければなりません。
参照元:環境省公式HP(https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_03.html)
実際の算定作業は3つのステップで進めます。特に、近年大幅な改定があった「排出係数」の取り扱いには、十分な注意が必要です。
最初のステップは、計算の基礎となる「活動量」のデータを収集することです。エネルギー供給事業者が発行する「検針票」や「請求書」、社有車の「給油伝票」などが、信頼性の高いデータソースとなります。対象期間(例:1年間)のデータを整理し、エネルギー種別ごとに使用量を集計します。
活動量のデータが準備できたら、対応する「排出係数」を特定します。この係数は環境省のウェブサイト「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」で毎年更新されており、直近では2025年3月18日の改定により電気の基礎排出係数が料金メニュー別で公表されるなど大幅な見直しが行われ、令和7年度(2024年度実績)の報告から適用されています。古い係数を使用した場合、算定結果が不正確になるだけでなく、温対法上の報告義務を満たさないリスクがあるため、報告年度と同じ年度の最新係数(PDFまたはExcel)を必ず参照してください。
従来、都市ガスには全国一律の係数が用いられていましたが、この制度は2024年度報告(令和6年提出分)から正式に廃止されました。現在は、電力と同様に、契約しているガス事業者ごとに定められた「事業者別排出係数」を使用する必要があります。
ガソリンや軽油など、主要な燃料の排出係数は2023年12月の改定(令和6年度報告から適用)で数値が更新され、そのままVer 6.0(2025年3月公表)マニュアルでも維持されています。
表1:主要燃料の排出係数の比較
| 燃料種 | 単位 | 変更前 (旧係数)※~令和5年度報告 | 変更後 (新係数)※令和6年度報告以降 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | t‑CO₂/kl | 2.32 | 2.29 | 「揮発油」として記載 |
| 軽油 | t‑CO₂/kl | 2.58 | 2.62 | – |
| 液化石油ガス (LPG) | t‑CO₂/t | 3.00 | 2.99 | – |
| 都市ガス | t‑CO₂/千Nm³ | 2.23 | 事業者別排出係数 | 全国一律係数の廃止 |
| ナフサ | t‑CO₂/kl | 2.36 | 2.27 | 参考:石化原料向け係数 |
電力の排出係数には「基礎排出係数」と「調整後排出係数」の2種類が存在し、報告目的に応じて適切に使い分ける必要があります。
発電所の燃料構成を直接的に反映した物理的なCO₂排出量を示す係数。
2025年3月18日の制度改定により、料金メニュー別の「メニュー別基礎排出係数(非化石電源調整済み)」として公表される形式に変更されました。
基礎係数に対し、非化石証書・J‑クレジット等の環境価値取引を反映(調整)した係数。
この2つの係数を正しく選択・併用することは、算定結果の信頼性と比較可能性に直結する重要な実務知識です。
| 報告目的 | 使用すべき係数 | 根拠・理由 |
|---|---|---|
| 温対法に基づく国への義務報告 | 基礎排出係数 + 調整後排出係数(両方) | 法令が物理排出量(基礎)と環境価値反映後(調整後)の双方報告を求めているため。 |
| CDP、SBTiなど国際イニシアチブ | 両方(ロケーション基準=基礎、マーケット基準=調整後) | GHGプロトコル Scope 2ガイダンスとCDP 2025質問書は“デュアルレポーティング”を必須化。 |
| サステナビリティレポート等での自主開示 | 調整後排出係数を中心に、基礎係数を併記することが推奨 | ステークホルダーに再エネ導入効果を示しつつ、物理排出量のトレンドも明示できるため。 |
| 取引先からの排出量開示要請 | 要請内容を確認のうえ両方提示が安全策 | 近年は取引先側でCDP/SBTスキームを採用し、デュアルレポートを求めるケースが増加。 |
計算・集計作業の効率化には、支援ツールの活用が有効です。特に、日本商工会議所が提供する「CO₂チェックシート」は、中小企業にとって有用な無料ツールです。
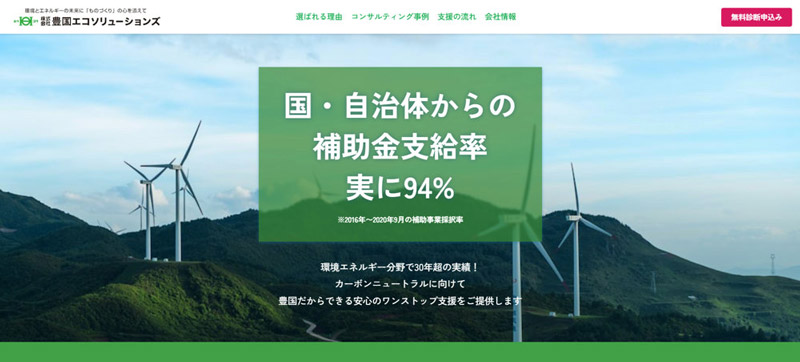
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。