このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
脱炭素コンサルティングの最大のメリットは、リスク管理と機会創出の両面から企業価値を高められることです。コンサルタントは、TCFDなどのフレームワークを用いた気候関連リスクの特定と対応策の立案をサポートします。
積極的な脱炭素化は事業機会も創出します。信頼性の高い脱炭素へのコミットメントはブランドイメージを向上させ、市場での差別化要因となります。印刷業界の大川印刷は、早期からの脱炭素経営でメディアの注目を集め、新規顧客獲得に成功しました。
また、脱炭素化は製品・サービス・プロセスの革新を促し、新たな収益源を生み出すことがあります。省エネ対策による運営コスト削減も重要なメリットで、山形精密鋳造は年間1,000万円以上の光熱費削減に成功しています。
さらに、グローバルな視点から脱炭素化の緊急性について客観的な認識を形成し、社内の旧弊な思考に挑戦する戦略的教育者としての役割も、コンサルタントの重要な価値の一つです。
脱炭素の起点は、GHGプロトコルに沿ったスコープ1・2・3の見える化です。ここまでは定石ですが、スコープ3は理屈だけでは進みません。
最初に立ちはだかるのは、立替や分散購買による購買実績の欠損、仕入先や品目の表記ゆれ・重複といったマスタ不統一、そして単位の混在です。
まずはベンダーマスタの名寄せと重複排除から着手します。続いて銀行明細・受入(GR)・総勘定元帳を突き合わせ、抜けを最小化します。品目からカテゴリへ移すマッピングは、UNSPSCと自社分類を併用したシンプルなルールを短期で定義し、例外はログ化して翌期に持ち越します。
未整備の領域は推計で補いますが、一次データと推定の境界を明確に区切ることが肝心です。
コンサルタントは企業のエネルギー消費パターンを詳細に調査し、無駄や非効率性を特定します。製造プロセス、設備の稼働状況、建物の断熱性能、照明・空調システムなど、あらゆる要素を対象に分析し、専門家の目で発見できる改善ポイントを明らかにします。
この分析に基づいて、投資対効果の高い省エネ施策を提案します。古い設備の更新、運用方法の改善、エネルギー管理システムの導入などの提案には、投資回収期間や年間削減コストといった財務的視点も含まれ、経営層に対して説得力のある形で投資の正当性を示します。
多くの企業で排出の大半はスコープ3に偏ります。
評価は“粗く広く”から始め、支出ベースでカテゴリ1(購入品)、4/9(輸送)、11/12(使用・廃棄)の寄与をパレートで把握します。
輸送の欠測は、出荷元・先の住所と重量から距離(t・km)を推定し、モードはWMSや購買条件の比率で暫定配分します。
翌期に向けてWMS/輸送管理へ「重量・距離・モード」の項目を追加し、推計→一次データの置換率をKPIとして管理します。
この置換を淡々と積み上げることが、監査対応力とレポートの信頼性の底上げにつながるでしょう。
コンサルタントは現状分析データを基に、中長期的な視点で実現可能かつ野心的な脱炭素化の道筋を設計します。このロードマップには短期・中期・長期の時間軸に沿った削減目標、主要施策、必要投資、組織体制の変革が体系的に盛り込まれます。
特に重要なのは、これが単なる環境部門の計画ではなく、企業経営全体と整合した戦略となることです。事業成長計画や設備投資計画と連携し、企業の持続的発展と脱炭素化の両立を図る内容となります。また、優れたロードマップは規制動向や技術革新に応じて定期的に見直す「生きた文書」としての性質を持ちます。
科学的根拠に基づいた目標設定のため、コンサルタントはSBT(Science-Based Targets)などの国際的フレームワークに準拠した目標設定とその達成に向けた行動計画の策定を支援します。
SBTはパリ協定の目標に整合した削減目標を設定するガイドラインです。コンサルタントは排出量ベースラインや成長計画に基づいて適切な目標を提案し、SBTイニシアチブからの認定取得プロセスも支援します。さらに、削減施策のポテンシャル評価、優先順位付け、実施スケジュールの立案、進捗管理の仕組み構築まで一貫してサポートします。
コンサルタントは脱炭素化に必要な投資計画の策定と費用対効果の詳細な試算を提供します。省エネ設備更新、再生可能エネルギー設備導入、エネルギー管理システム構築などの選択肢について、初期投資額、運用コスト、CO2削減効果、投資回収期間を含めた経済性評価を行います。
また、政府の補助金や税制優遇の活用可能性も検討し、企業の実質的負担を最小化する方策も提案します。短期的リターンが見込める施策と中長期的な競争力強化につながる施策をバランスよく組み合わせた包括的な投資ポートフォリオを設計し、財務的リターンだけでなく、顧客評価向上や人材確保などの間接的メリットも含めた総合的な投資価値評価を行います。
コンサルタントは省エネルギー施策と再生可能エネルギー導入の両面から、技術選定から導入後の効果検証まで一貫した支援を提供します。省エネ対策としては、生産設備の高効率化、空調・照明システムの最適化、熱回収システムの導入などを提案し、「投資ゼロの省エネ」として運転条件最適化や従業員の意識改革も重視します。
再エネ導入では、自家消費型太陽光発電、コージェネレーションシステム、オフサイトでの再エネ調達など、最適な方法を選定します。特にPPA(電力購入契約)モデルは初期投資ゼロで再エネを導入できる方式として注目されています。専門的知識と経験を持つコンサルタントの支援により、技術導入リスクを最小化し確実な効果を得ることができます。
持続的な脱炭素化には適切な社内体制構築が不可欠です。コンサルタントは脱炭素推進チームの編成や部門横断的な委員会設置など、適切な推進体制の構築を支援します。環境部門だけでなく全部門を巻き込んだ体制と経営層の関与確保が重要です。
また、目標達成に向けた役割と責任の明確化、進捗管理の仕組み、意思決定プロセスなどのガバナンス構造設計も支援します。さらに、各層に応じた教育・研修プログラムの設計と実施により、必要なケイパビリティを社内に構築します。コンサルタントは「外部の目」として客観的視点から社内課題を指摘し、全社一丸となった取り組みを実現する触媒となります。
コンサルタントは、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを回すためのPDCAシステムの構築を支援します。まず、エネルギー使用量、CO2排出量、関連コストなどの定量データを効率的に収集・分析するプロセスやツールの導入をサポートします。
次に、データに基づく進捗評価と課題抽出の方法論を確立し、目標に対する達成度評価、未達の原因分析、新たな削減機会の特定などを行います。さらに、経営層への報告体制や全社への情報共有の仕組みも整備します。
多くのコンサルタントが提供する「伴走支援」は、PDCAサイクルの定着を目的としており、定期的なレビュー会議の開催、改善策の提案、成功事例の横展開など、計画倒れに終わらせない継続的なフォローアップを行います。
コンサルタントとの初期対話を効果的にするため、まずは自社のCO2排出量の大まかな全体像を把握しておきましょう。自社の主要なエネルギー使用ポイントを特定し、おおよその使用量を把握します。工場なら製造設備や空調・照明の電力使用量、ボイラーや車両の燃料使用量が主な対象です。オフィスであれば、電力・ガスの使用量、社用車の燃料使用量などが基本項目となります。
これらの情報を基に、経済産業省や環境省が提供する排出係数を用いて簡易的なCO2排出量換算を行うと良いでしょう。この段階では精度よりも、「どの活動からどの程度の排出があるのか」という全体像の把握が目的です。
コンサルタントとの協働をスムーズにするため、自社のエネルギー使用データを事前に整理しておきましょう。過去1〜3年分の電気・ガス・燃料の請求書や使用量データを収集し、月別・拠点別・用途別に分類しておくと効果的です。
また、生産量や営業時間、気温など、エネルギー使用量に影響を与える要因のデータも整理しておくと、より深い分析が可能になります。過去に実施した省エネ対策や設備投資の記録も重要な情報です。これらのデータが電子化されていない場合は、可能な範囲でエクセルなどに入力しておくことをお勧めします。
これまでに実施してきた環境関連の取り組みや現在進行中の施策を整理しておくことも重要です。環境マネジメントシステム(ISO14001など)の導入状況や環境方針・目標の有無、これまでに実施した省エネ対策や再エネ導入の取り組みとその効果・課題点を把握しておきましょう。
また、環境関連の情報開示状況や、社内の推進体制・人材の状況も確認しておきます。これらの情報を整理することで、自社が脱炭素化の道のりのどの段階にいるのかを客観的に把握し、次のステップを明確にイメージすることができます。
脱炭素コンサルタントとの協働を成功させるためには、自社がなぜ脱炭素に取り組むのかという根本的な理由を明確にしておくことが重要です。法規制への対応、顧客や取引先からの要請、投資家からの期待、コスト削減、新規市場開拓、企業ブランド向上、社会的責任など、様々な理由の中でどれが自社にとって最も重要かを経営層で議論し、優先順位を付けておきましょう。
例えば、主要顧客からサプライチェーンのCO2削減を求められているのであれば、その要求水準やタイムラインを正確に把握しておくことが重要です。コスト削減が主目的なら、エネルギーコストの現状と将来予測、削減ポテンシャルの概算を把握しておくことが有効です。
自社が達成したい目標の大枠とスケジュールを検討しておくことも重要です。目標設定においては、「2030年までにCO2排出量を50%削減(2020年比)」といった定量的な指標と達成期限を含めることが望ましいです。この段階では暫定的な目標で構いませんが、短期・中期・長期のマイルストーンも検討しておくと良いでしょう。
スケジュール検討の際には、自社の事業計画や設備投資サイクルとの整合性も重要です。工場の新設や大規模改修のタイミング、製品開発サイクル、中期経営計画の策定時期などと脱炭素化の取り組みを連動させることで、効率的な推進が可能になります。
脱炭素化への取り組みには、コンサルティング費用だけでなく実際の対策実施のための投資も必要です。コンサルティングの種類や範囲によって費用は異なりますが、基本的な排出量算定や簡易的な戦略策定であれば数十万円から、包括的な戦略立案や長期的な伴走支援となると数百万円以上になることもあります。
実際の対策実施に必要な投資枠や投資判断の基準(例:投資回収期間は5年以内)も事前に整理しておくと良いでしょう。また、政府の補助金や低利融資などの活用可能性も考慮に入れ、投資だけでなく期待されるリターン(エネルギーコスト削減額など)も併せて検討することが重要です。
脱炭素コンサルティングを効果的に活用するためには、コンサルタントと協働し社内での実行を担うプロジェクトチームの編成が不可欠です。理想的なチームは環境部門だけでなく、経営企画、財務、製造、調達、営業など様々な部門からのメンバーで構成されます。特に、実際にエネルギーを使用する現場部門や設備投資の意思決定に関わる部門の参加が重要です。
プロジェクトリーダーには、環境に関する専門知識だけでなく、社内の様々な部門と調整できる能力や経営層との円滑なコミュニケーションができる立場にある人材が望ましいでしょう。チームメンバーの役割と責任を明確にし、プロジェクトにどの程度のリソースを割くことができるかも事前に確認しておく必要があります。
脱炭素化の取り組みを成功させるためには、経営層の明確なコミットメントが不可欠です。経営層に対して脱炭素化の必要性と期待されるメリットを明確に説明し、共通認識を形成しましょう。経営層が主導的に関与する体制を整えることが重要で、定期的な進捗報告会議を設定したり、重要な意思決定の場に経営層が参加する仕組みを作ったりすることで継続的な関与を確保します。
必要なリソース(人員、予算、時間)の確保についても事前に経営層の承認を得ておくことが重要です。経営層のコミットメントは社内の他部門の協力を得る上でも重要で、トップの明確な意思表示があることで各部門も積極的に協力する姿勢を持ちやすくなります。
必要な情報やデータを効率的に収集・提供できる体制を整えておくことも重要です。エネルギー使用データ、設備情報、生産・営業データなどが主な対象となりますが、これらの情報を誰がどのように収集するかの役割分担を明確にしましょう。
データの信頼性と一貫性を確保するための仕組みも重要です。測定方法の標準化、データチェックのプロセス、責任者による承認フローなど、質の高いデータを継続的に収集するための体制を整えましょう。こうした情報・データ収集の体制は、コンサルティング期間中だけでなく、その後の継続的な脱炭素化の取り組みにおいても重要な基盤となります。
脱炭素コンサルタントには、業界特化型と総合型があります。業界特化型は特定の業界における脱炭素化の課題と解決策に精通し、同じ業界の特有のプロセスや設備に関する深い知識を持っています。特に製造プロセスが複雑で特殊な業界では、業界特化型コンサルタントの価値が高くなる傾向があります。
一方、総合型コンサルタントは幅広い業界での支援経験を持ち、多様な視点や異業種のベストプラクティスを提供できる強みがあります。経営戦略との統合や組織変革などの横断的なテーマに強みを持つことが多く、脱炭素化を全社的な変革として捉える場合に適しています。
選択の際には、自社の課題の性質を考慮することが重要です。技術的・専門的な課題が中心であれば業界特化型、経営戦略や組織変革に関わる課題が中心であれば総合型が適しているケースが多いでしょう。
コンサルタント選びにおいて、過去の成功事例と実績は信頼性と能力を示す重要な指標です。候補となるコンサルタントの支援実績の数と質を確認し、特に自社と似た規模や業種、課題を持つ企業の事例があれば参考になります。
成功事例を評価する際には、CO2削減量、エネルギーコスト削減額、投資回収期間の実績、SBT認定取得やCDPスコア改善などの外部評価向上といった定量的な成果指標に着目しましょう。また、長期的な関係を築いている顧客の存在も重要な指標です。
さらに、コンサルタントが直面した困難や課題、そしてそれをどのように乗り越えたかという点も重要です。面談の際には、こうした「失敗から学んだこと」についても質問してみると良いでしょう。
脱炭素コンサルティングの領域では、専門的な知識と技術が不可欠です。エネルギー管理士、環境計量士、カーボンマネジャーなどの資格や、GHGプロトコル、SBTi、TCFDなどの国際的フレームワークに関する知識と経験を確認しましょう。
また、省エネルギー技術、再生可能エネルギーシステム、エネルギーマネジメントシステムなどの技術的専門知識や、投資回収計算、費用対効果分析などの財務・経済分析の能力も重要な要素です。
コンサルタント自身の継続的な学習姿勢も評価ポイントです。脱炭素の分野は技術革新や政策変更が急速に進む領域であり、最新動向に常にアップデートしている姿勢があるかどうかは重要な判断材料となります。
コンサルタントが提供するサービスの全体像を把握し、自社のニーズに合致した範囲をカバーしているかを確認しましょう。基本的なサービスとしては、CO2排出量の測定・算定、削減戦略の立案、実行支援、情報開示の支援などがあります。
また、SBT認定取得支援、TCFD提言に基づく情報開示、サプライチェーン排出量の算定、再生可能エネルギー調達戦略、補助金申請支援など、特定の専門領域に強みを持つサービスがあるかも確認します。自社の優先課題に合致した専門性を持つコンサルタントを選ぶことで、より効果的な支援が期待できます。
サービス提供方法にも注目しましょう。現場に入り込んでの「伴走支援」型か、定期的なアドバイスを提供する「顧問」型か、明確な成果物を納品する「プロジェクト」型かなど、支援スタイルは様々です。自社の体制や課題に合った支援方法を選ぶことが成功への鍵となります。
脱炭素コンサルティングの費用は、サービスの種類と範囲によって大きく異なります。一般的な料金モデルとしては、GHGデータ管理ツールなどを月額または年額で提供する「SaaSサブスクリプション」型(年間数万円から30万円程度)、明確な成果物が定義された特定のプロジェクトに対して料金を設定する「プロジェクトベース」型(数十万円から数百万円)、継続的な戦略アドバイザリーサービスを月額固定料金で提供する「リテイナー(顧問契約)」型(月額12万円程度から)、そして補助金申請支援などで採用される「成功報酬」型(獲得補助金額の10〜30%程度)があります。
コンサルタント選びでは、これらの料金体系の詳細と、具体的に何が含まれ何が含まれないかを明確に確認することが重要です。また、見積もりの透明性も重要な評価ポイントです。工数や単価の内訳が明確に示されているか、前提条件や範囲が明示されているかなどを確認しましょう。
脱炭素への取り組みは継続的な改善が必要なプロセスであり、コンサルティング期間後のアフターフォローの充実度も重要な判断基準です。納品物やレポート提出後のフォローアップ内容、継続的な情報提供やアップデートの仕組み、初期プロジェクト完了後の継続サポートオプションの有無と内容を確認しましょう。
また、コンサルタントのネットワークや紹介能力も考慮に値します。初期のコンサルティング後により専門的な分野のサポートが必要になった場合に、適切なパートナーを紹介してくれる関係性があるかどうかも、長期的な価値を生み出す要素となります。
脱炭素コンサルティングは企業変革を支援するパートナーシップであり、担当者との人間的な相性はプロジェクトの成功に大きく影響します。初回面談や提案プレゼンテーションの段階で、担当者のコミュニケーションスタイルや人間性を観察し、自社の文化や価値観と合致しているか、率直かつ建設的な対話が可能か、信頼関係を構築できそうかを評価しましょう。
また、担当者の傾聴能力と理解力、複雑な専門用語や概念を分かりやすく説明できる能力、プロジェクト管理能力も確認すべきポイントです。長期的なパートナーシップを見据えた場合、担当者の継続性やプロジェクト途中での担当者変更の可能性についても事前に確認しておくと良いでしょう。
定期的かつ質の高いレポーティングは、プロジェクトの透明性と成果を確保する上で重要です。レポーティングの頻度と形式(週次、月次、四半期ごとなど)、レポートの内容と質を評価しましょう。過去のクライアントに提供したレポートのサンプルを確認できれば理想的です。
また、異なるステークホルダー向けのレポーティング対応や、緊急事態や重要な発見があった場合の臨時報告の仕組みも確認しておくことが望ましいです。レポーティングのカスタマイズ性も評価ポイントで、自社の特定のニーズや関心事項に合わせてレポートの内容や形式を調整する柔軟性があると効率的なコミュニケーションが可能になります。
脱炭素への取り組みでは予期せぬ課題や状況変化に直面することも多く、コンサルタントの柔軟な対応力は極めて重要です。スコープや要件の変更に対する柔軟性、問題解決能力と創造性、社内の体制や文化に合わせたアプローチの調整能力を評価しましょう。
また、技術やトレンドの進化に対する適応力や、急な報告要請や期限が迫った対応が必要になった場合の緊急対応能力も確認しておくと良いでしょう。過去のプロジェクトで直面した困難とその克服方法について質問してみると、対応力を把握する手がかりになります。
脱炭素コンサルティングの費用は、サービスの種類、企業規模、プロジェクトの複雑さによって大きく異なります。基本的な排出量算定や簡易的な診断サービスであれば30万円〜100万円程度、SaaSベースの排出量管理ツールは年間数万円〜30万円程度が相場です。
より包括的なサービスとなると費用は上昇し、Scope3を含む詳細な排出量算定では中小企業でも150万円程度、SBT認定取得支援は240万円以上からとなります。戦略的なコンサルティングサービス(TCFDに基づく気候リスク分析など)は200万円〜500万円以上、全社的な脱炭素ロードマップ策定は300万円〜1,000万円以上となるケースもあります。
継続的な支援を受ける場合の月額顧問料は12万円〜50万円程度が相場で、補助金申請支援については成功報酬型の料金体系が多く、獲得補助金額の10%〜30%程度が一般的です。公的機関や地方自治体が提供する支援サービスには無料または低廉な価格で利用できるものもあり、特に中小企業の場合は初期段階で活用を検討すると良いでしょう。
脱炭素コンサルティングのプロジェクト期間も取り組みの範囲や深度によって異なります。基本的な排出量算定(Scope1・2)のみであれば1〜3ヶ月程度、Scope3を含む包括的な排出量算定では3〜6ヶ月程度かかります。
戦略立案フェーズについては、シンプルな削減計画で2〜3ヶ月程度、SBT認定取得を目指す場合は準備から承認まで6〜12ヶ月程度を見込む必要があります。TCFDに基づく気候リスク分析やシナリオ分析は3〜6ヶ月程度、包括的な脱炭素ロードマップの策定は6〜12ヶ月程度が一般的です。
実行段階のサポートについては、省エネ診断とその改善支援で3〜6ヶ月程度、再生可能エネルギーの導入支援で6〜12ヶ月程度、全社的な脱炭素推進体制の構築と定着支援で12〜24ヶ月程度を目安とすることが多いです。情報開示支援については、CDPへの回答支援で2〜3ヶ月程度、サステナビリティレポートの作成支援で3〜6ヶ月程度が一般的です。
なお、これらの期間はあくまで目安であり、企業の規模、業種、既存のデータ整備状況、社内リソースの投入度合いなどによって大きく変動します。また、多くの場合、初年度は基盤構築に時間がかかりますが、2年目以降は効率化されることが多いです。
脱炭素コンサルティングへの投資から最大の価値を引き出すためのポイントとしては、まず自社の準備と明確な目標設定が重要です。基礎データの整理や自社課題の明確化などの事前準備により、コンサルティングの効率が高まります。
また、適切なスコープと段階的なアプローチの設定も効果的です。すべてを一度に解決しようとするのではなく、最も重要度や緊急度の高い領域から段階的に取り組むことで投資効率を高められます。さらに、社内リソースとコンサルタントの役割分担の最適化も重要で、自社でできる作業は自社で担当し、コンサルタントの専門性が最も発揮される領域に集中してもらうことで費用対効果を高めることができます。
複数の提案の比較検討、公的支援制度の活用、長期的なパートナーシップの構築も効果的な方法です。また、コンサルティングプロジェクトを単なるサービス購入ではなく社内の能力構築の機会と捉え、知識やスキルを吸収して将来的には自社で対応できる領域を増やしていくという視点も重要です。
脱炭素経営は、もはや環境対策の枠を超え、企業の存続と成長に直結する戦略的課題となっています。規制の強化、投資家の要請、サプライチェーンからの圧力など、複合的な要因が企業に脱炭素化を促しており、この道のりを効果的に進むためには専門的な知見を持つ脱炭素コンサルタントの活用が鍵となります。
コンサルタントは、CO2排出量の測定・算定から戦略立案、実行支援、情報開示まで、脱炭素化の全プロセスをサポートします。彼らの専門性と経験を活用することで、限られたリソースでも効率的かつ効果的に脱炭素経営を実現できます。特に、知識・人材のギャップ、財務的投資のリスク、社内合意形成という三つの主要な障壁を乗り越える上で、コンサルタントは戦略的なイネーブラーとなります。
コンサルタント選びでは、専門性と実績、サービス内容と料金体系、相性とコミュニケーションといった多角的な視点での評価が重要です。自社の状況や課題に最も適したパートナーを選ぶことで、投資に見合う価値を得ることができるでしょう。
脱炭素への取り組みは一朝一夕で完了するものではなく、継続的な改善が必要なプロセスです。しかし、適切なパートナーシップと戦略的なアプローチによって、この課題を企業価値向上の機会へと転換することができます。今こそ、自社の現状を見つめ直し、脱炭素への道のりを歩み始める時です。
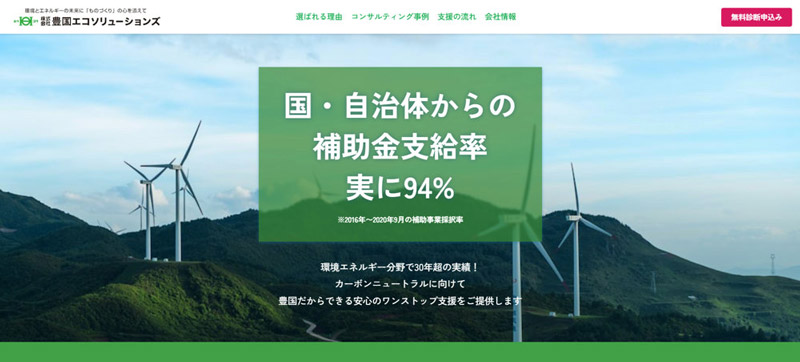
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。