このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
人間の企業活動や日常生活などによって、CO2をはじめとする温室効果ガスはどうしても排出されてしまいます。このやむを得ない排出量を、他の場所で実施されている温室効果ガスの削減・吸収のための活動に出資することで埋め合わせる(オフセットする)ことができる仕組みをカーボンオフセットと言います。
カーボンオフセットが必要なのは、CO2を含む温室効果ガスの排出量削減が喫緊の大きな課題となっているからです。「排出量への埋め合わせ」という形で、植林活動や森林管理、再生エネルギーの利用といった排出削減の取り組みへの投資につなげることで、地球温暖化の抑制を促します。
カーボンオフセットの取り組みを進めるためには、次のようなプロセスを経る必要があります。
こうした取り組みには、十分な情報提供と透明性を確保する必要があり、まずは、経済活動や日常生活等での排出量を把握するため、環境省が定める規準に従って計算します。その上で排出量の削減に取り組み、それでもやむを得ず排出してしまう量を把握した上で、これに見合う分を埋め合わせます。
埋め合わせには、温室効果ガスの吸収量や削減量を「クレジット」として取引する仕組みが使われており、日本では「J-クレジット制度」が導入されています。
カーボンオフセットとよく似た言葉に「カーボンニュートラル」があります。
カーボンオフセットが温室効果ガスの排出量を環境への投資で埋め合わせる取り組みを指すのに対し、カーボンニュートラルは温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、全体としての排出量を実施的にゼロにすることを指します。カーボンニュートラルを実現するための取り組みの一つが、カーボンオフセットという位置づけです。
鳥取県日南町では、道の駅で生じるCO2全量を、町有林由来のJ-クレジットに加え、販売する商品に付与したクレジットによってオフセット。地元の森林由来のJ-クレジットがある自治体では、ふるさと納税の返礼品メニューに「カーボンオフセット」を挙げているところもあります。
スカンジナビア航空は、カーボンオフセットを希望する乗客がチケット購入時にクレジットを購入できる仕組みが整えられています。同種の仕組みは、ブリティッシュ・エアウェイズやエア・カナダなど多くの航空会社に広がっています。
カーボンオフセットは、温室効果ガス削減に取り組んだ上での最終手段という位置づけなのに、クレジットが「免罪符」のような存在となり、排出量削減の努力を怠ることにつながってしまうことが課題として挙げられます。排出量の算出方法が事業者ごとにバラバラであるいう問題もあります。
カーボンオフセットを進めることは、中小企業にも自社のブランディングにつながるなど大きなメリットがあります。実効あるオフセットのためには、排出量の把握と削減にしっかり取り組みましょう。
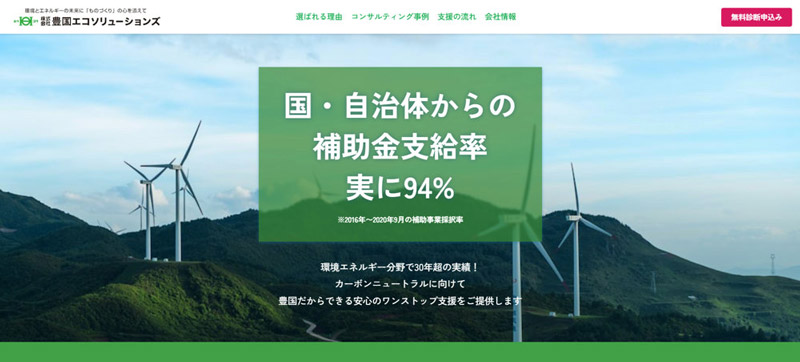
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。