このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
令和7年度には、カーボンニュートラルや脱炭素社会の実現をめざす取り組みとして、多様な補助金制度が用意されています。再生可能エネルギーの導入支援や地域の脱炭素化を進めるプロジェクト、事業場での省CO₂化に貢献するものなど、その領域は幅広いです。
ここでは、5つの補助金を取り上げ、それぞれの対象となるプロジェクトや応募資格、想定予算の概要をご紹介します。
地域脱炭素推進交付金は、地方公共団体と民間事業者が協働し、再生可能エネルギー導入や地域全体の脱炭素化に取り組む事業を支援する制度です。各地域の特性を生かした施策を促進し、先行的に脱炭素に取り組む「脱炭素先行地域」の展開を加速する役割を担います。具体的には、地域のCO₂排出削減を後押しするプロジェクトや、再エネ導入における課題解決に向けた取組みを想定しています。
交付対象は、地方公共団体および民間事業者・団体などです。申請時には脱炭素先行地域に選定されていることや再エネ導入設備の規模が一定以上であることなどが主な要件となります。
脱炭素先行地域づくりや特定地域脱炭素移行加速化交付金(GX)への活用などが中心です。具体的には大規模太陽光発電や地域熱供給システム、マイクログリッドの導入、省エネ設備の普及、および事業計画全体の評価・検証なども含みます。
令和7年度の公募スケジュールは、環境省の公式HPで今後公表される予定です。例年、年度当初や夏頃に複数回の公募が実施されるケースがあるため、最新情報を確認することをお勧めします。
交付率は原則として事業費の2/3です。対象事業や地域の状況によって加算や要件が変動する場合があるため、詳細は公募要領をチェックしてください。
交通や建築物、再生可能エネルギー、資源循環など、複数セクターを横断して技術開発や実証研究を行う取り組みを支援する制度です。地域ならではの特徴を活かし、セクター同士の連携で効率的な脱炭素技術を生み出すことを狙いとしています。
公募対象は民間企業だけでなく、大学や研究機関、団体など幅広く含まれます。大規模から小規模まで、革新的な技術や事業モデルを目指すプロジェクトであれば応募しやすい仕組みです。
研究開発や実証に関して地域共創型やボトムアップ型などのテーマが設定されています。具体的には気候変動対策と農林水産や交通を連動させる実証や、CO₂削減効果の高い技術の事業化を支援するボトムアップ型のアプローチなどが中心です。
公募期間は令和7年1月9日(木)~同年2月7日(金)15:00までとされており、直近の公募要領を確認の上、期日や提出書類を把握しておく必要があります。
1事業あたり概ね3,000万円から5億円程度が目安とされ、補助率は事業費の1/2までとされています。事業規模に応じて手厚い支援が受けられる点も特徴です。予算総額は環境省の公表データを参照してください。
太陽光発電やバイオマス発電などを中心とした再生可能エネルギーの導入とコスト低減を図る事業を支援します。地域のエネルギー自給率を高める点と再エネの普及促進が大きな目標です。太陽光パネルと蓄電池の組み合わせやソーラーカーポート導入なども支援対象となります。
対象となるのは、以下の条件を満たす自治体です。
複数自治体による共同申請も可能で、その場合は代表機関が申請書類を提出します。
支援内容は多岐にわたり、太陽光発電やバイオマス・地中熱など多様な再エネ導入を含みます。地域再エネ目標の策定や住民参加型プロジェクトの開発など、ソフト事業も対象です。
補助率は定額(10/10)で、1事業あたりの上限額は自治体区分によって異なります。
民間施設を活用した連携事業などの場合は、上限が異なる場合もあるため、公募要領で詳細を確認してください。
SHIFT事業は、工場や事業場の省CO₂化を大きく進展させるための制度です。設備の電化や燃料転換、既存設備の高効率化、DX技術を用いた省エネ管理など、幅広い投資を支援対象としています。単体の排出量削減だけでなく、サプライチェーン全体への波及効果が重視されることもあります。
主に工場や事業場を運営する民間企業などが応募可能です。省エネ設備の導入や一括更新などが典型的な事例として挙げられます。
支援の柱となるのは、省CO₂型設備への更新やAI・IoTを活用した最適運転です。排熱利用や高効率機器への交換、企業間連携によるScope3排出量削減プロジェクトなど、多様な取り組みが想定されます。
令和7年度は、例年通り年度当初か秋頃に公募が始まる見込みです。年度中に追加公募が行われる可能性もあるため、環境省の公式HPを確認してください。
予算規模は年度によって変動します。大規模な省CO₂設備投資に対して高い補助上限を設定することが多いものの、詳細は公募要領の正式発表を待つ必要があります。
補助率や上限額は事業区分ごとに異なるため、主な例を以下に示します。
本事業は、防災拠点や避難所となる公共施設に再生可能エネルギーや自立型エネルギー設備を導入し、非常時の電力供給と平常時のCO₂排出削減を両立させるものです。太陽光発電・蓄電池やコージェネレーションシステム(CGS)を組み合わせることで災害時の最低限の電力を確保し、地域の防災力を高める狙いがあります。
地方公共団体(都道府県、市区町村など)が中心となり、地域防災計画で避難所や防災拠点に位置づけられている公共施設を保有・運営する団体が該当します。
導入する設備としては、太陽光発電やバイオマス、地中熱利用設備、CGSなどの自立・分散型エネルギーが挙げられます。非常時の電源確保と日常の省CO₂を両立するため、蓄電池の設置や省エネ装置の導入も同時に行う場合が多いです。
令和7年度の募集は令和7年1月22日から同年1月31日までが予定されています。ただし、年度途中で補正予算に伴う追加公募が実施される可能性もあります。
過去には1,000億円規模の予算が配分された例がありますが、令和7年度の正式な予算額は公募要領公表後に確定します。導入する設備によって補助率が異なるケースがあるため、詳細な条件は環境省の公式情報を確認してください。
カーボンニュートラルや脱炭素のための補助金・助成金を活用するには、まず各制度の募集時期や条件をよく調べることが大切です。
支援対象となる技術や取組内容、削減見込みのあるCO₂排出量など、求められる要件は制度ごとに異なります。また、人気が高い補助金ほど競争率が上がり、早期の申請や計画内容の明確化が成功の鍵となるケースが少なくありません。
一方で、申請書類の作成には専門的な知識を要する場合が多く、CO₂削減目標や具体的なアクションプランをどのようにまとめるかが重要になります。環境負荷の低減策をわかりやすく説明し、成果を定量的に示すことが求められるため、情報収集や書類作成に時間がかかることもあります。
こうした申請業務に自信がない場合は、脱炭素や省エネに特化したコンサルタントの活用を検討するのがおすすめです。専門家は常に最新の助成制度を把握しており、書類の作成や計画のブラッシュアップをサポートしてくれます。複雑な要件に対応しながら自社の強みを引き出し、採択の可能性を高めるアドバイスを受けられるのは大きなメリットとなるでしょう。
補助金や助成金のハードルは決して低くありませんが、専門家と協力しながら綿密に計画を立てることで、環境面と経営面の両方で大きな成果を得られる可能性が高まります。
複数省庁やSII等の執行団体が運営する補助金の基本フローを、要点と必要書類に分けて視覚化しました。
「交付申請→審査→交付決定→(必要に応じて変更承認)→実績報告→額の確定→請求→交付」の順で進みます。
公募要領で対象事業・補助率・上限額・スケジュール・必要書類を確認し、工期や納期から逆算して計画を立てます。
GビズID(gBizID)を取得し、jGrantsにログイン。案件管理・申請状況の確認を行います。
審査では、省エネ効果・費用対効果・実現可能性等を評価。jGrantsで採択・概算払・額の確定などのステータスを確認できます。
競争性の確保に留意しつつ契約・調達を実施。調達プロセスの記録を残し、変更が生じる場合は事前に変更承認を取得します。
納品・支払い・稼働の証憑を整理し実績報告。検査後に補助金額が確定し、請求→交付へ。原則精算払い、制度により概算払いも可。
取得資産には処分制限期間(原則法定耐用年数)があり、売却・転用等は事前承認が必要。書類は事業完了年度終了後5年間の保存義務があります。
カーボンニュートラル関連補助金を活用する際には、陥りやすい落とし穴があります。実務上特に注意すべきポイントを整理していきましょう。
重要な注意点は、交付決定前の発注・契約・着工が原則として認められないことです。交付決定通知前に発注等を完了した案件は補助対象外となり、全額が自己負担となってしまいます。ただし、翌年度着手承認など特別な手続きが規定されている事業もあるため、公募要領での確認が必要です。
工期や納期の都合で早期着手が必要な場合でも、安易に先行着手してはいけません。必ず交付決定を待ってから契約・発注を行うよう、社内の調達部門や施工業者との調整を徹底する必要があります。
消費税は原則として補助対象外となるため、見積書や内訳書では税抜きベースで対象経費を切り分ける必要があります。また、建屋躯体工事や撤去費、交付決定前に発生した調査費なども多くの制度で対象外となっています。
補助対象経費の範囲は「設計費」「設備費」「工事費」などで正確に区分し、対象外経費を混在させないよう注意が必要です。特に、仕様書で特定メーカーや機種を指定することは避けなければなりません。見積もりや入札において競争性を阻害する仕様付けは認められず、結果的に特定製品に限定される場合も問題となることがあります。
多くの制度では、一定金額以上の契約において3社以上の見積比較が要求されます。しかも、補助対象経費ごとに最安値での選定が原則となっており、書類の日付の前後関係や承認前着手の有無も厳密に調査されます。
支払い方法にも制限があり、手形払いや割賦払いは認められません。銀行振込のみが原則となっており、実績報告後の書面審査や必要に応じた現地調査を経て、精算払いで振り込まれます。前払いは原則として認められないため、資金繰りの計画も重要です。
同一設備に対する国の補助金どうしの併用は原則として不可となっています。地方自治体の補助制度については、国費充当分を除いて併用可能とされる例が多いですが、各制度の要綱で個別に確認する必要があります。
東京都などの地方制度でも、都内の別の助成制度との併用不可や減額調整などの個別規定があります。また、FIT(固定価格買取制度)やFIP(フィードインプレミアム)、Jクレジットとの関係も制度ごとに条件が異なるため、重複カウントや譲渡制限に注意が必要です。
2025年度からは、GX(グリーントランスフォーメーション)要件が追加されています。工場・事業場型や電化・脱炭素燃転型では、GX推進に係る取組の表明や、一部事業者では省エネ法定期報告情報の開示制度への参加が申請要件となっています。
省エネ法の「定期報告情報の開示制度」では、EEGS(エネルギー効率化支援システム)上で参加宣言と開示を行う必要があります。対象事業者は宣言期限や入力期間を厳守しなければならず、スケジュール管理がより複雑になっています。
CO2削減量や一次エネルギー削減量の算定根拠は、ベースライン設定、実測データ、計測期間などを明確にする必要があります。たとえば、高効率給湯器の導入では1週間以上のエネルギーデータの提出が求められるなど、具体的な計測要件が設定されています。
計画未達や データ未取得の場合は補助金返還の対象となる可能性があるため、実現可能な計画立案と確実なデータ取得体制の構築が不可欠です。ZEB化事業では、交付決定前の設計契約は対象外となるなど、細かな経理・手続きルールにも留意する必要があります。
主な制度として、経済産業省系では「省エネ・非化石転換補助金」があり、工場・事業場全体の更新や燃料転換、EMS(エネルギーマネジメントシステム)などが対象となります。国土交通省系では「既存建築物省エネ化推進事業」として、非住宅建築物の断熱・設備等の改修を支援しています。
また、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)実証事業では、新築・改修でZEB化を目指す案件が対象となります。環境省系の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」は主に自治体向けですが、企業は自治体事業への参画を通じて恩恵を受けることができます。
省エネ・非化石転換補助金の大型案件では、上限が数十億円規模(連携・複数年度含む)となるケースもあります。省エネ投資促進支援(設備単位型)では、補助率1/3以内、上限1億円が代表的な設定です。既存建築物省エネ化推進事業(国土交通省)では、補助率1/3、上限5,000万円/件となっています。ZEB実証事業については、年度・区分ごとに上限や要件が設定されるため、公募要領での確認が必要です。
省エネ効果やエネルギー削減量の定量基準が必須となります。例として、設備単位型(Ⅲ型)では「省エネ率10%以上」かつ「削減量1kL以上(原油換算)」といった基準が設定されています。工場・事業場型では、省エネと非化石割合、または原単位改善率などで基準が定義されます。既存建築物省エネ化推進事業では、改修により20%以上の省エネ効果が目安となっています。
原則として設備費が中心となり、場合により工事費や計測・EMS関連費用が認められます。ただし、制度や枠組みによって対象範囲が異なるため、毎回公募要領での確認が必要です。重要なのは、消費税が原則として補助対象外である点で、見積書や内訳書では税抜きベースでの切り分けが求められます。
導入後にエネルギー使用量と省エネ効果の実測報告が必要となります。計画未達やデータ未取得の場合は返還対象となる可能性があるため、確実なデータ取得体制の構築が不可欠です。計測期間や計測方法についても、公募要領で定められた基準に従う必要があります。
会計検査院や所管省庁の検査対象となります。完了後も帳票・証憑の保存が必要で、SIIの事務取扱等でも検査対象である旨が明記されています。書類は原則として5年間の保存義務があり、適切な管理体制を維持する必要があります。
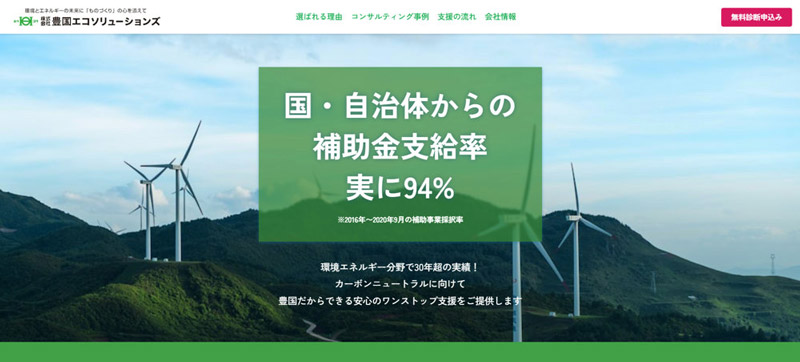
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。