このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
日本における主要産業の一つである一方、二酸化炭素排出量も多い自動車業界では、自動車メーカーが中心となってカーボンニュートラルへの取り組みを積極的に進めています。ここでは、自動車業界・自動車メーカーにおけるカーボンニュートラルの対応動向や取り組み事例をご紹介します。

自動車業界では、中長期的な戦略として新車の電動化の取り組みを推進しています。他国では急速にEVが普及しているところもある一方、日本は少々遅れていると言わざるをえません。しかし、自動車メーカーではEVの開発に多額の資金を投じており、ガソリン車・ハイブリッド車からEVへと転換する流れが起きています。
また、水素やバイオエタノールといったクリーンエネルギーの開発にも積極的ですが、ステーション整備や商業化に向けたコストが課題になっています。カーボンニュートラルをより強く推進するためには、官民の連携や他業界を巻き込んだ取り組みが必要といえるでしょう。
多くの企業がカーボンニュートラルへの取り組みの重要性を認識しつつも、具体的な行動に移せないケースが見られます。
その背景には、いくつかの共通した課題が存在します。これらの壁を理解し、乗り越えることが、カーボンニュートラル実現への第一歩となります。
カーボンニュートラル達成に向けた最初の関門は、具体的かつ実行可能な目標設定の遅れです。
多くの場合、国際的な規制や法規の解釈が複雑で、企業内で統一された理解を形成するのに時間を要します。その結果、部門ごとにカーボンニュートラルへの取り組みの優先順位が異なり、全社的な戦略としての一貫性が失われがちです。
「2050年カーボンニュートラル」という長期的なスローガンは共有されても、そこに至るまでの中間目標や具体的なアクションプランが曖昧なままでは、実質的な進展は期待できません。
また、電気自動車(EV)へのシフトがカーボンニュートラルの主要な手段として注目されるあまり、"とりあえずEV"といった施策に偏ってしまう傾向も見受けられます。
しかし、自動車のライフサイクル全体でCO2排出量を削減するためには、製造プロセスや物流段階での排出量削減も同様に重要です。これらの分野での取り組みが後回しにされることで、企業全体のカーボンニュートラル達成が遅れるリスクがあります。真のカーボンニュートラルは、製品だけでなく、事業活動全体の変革によって達成されることを認識する必要があります。
カーボンニュートラルへの具体的な施策を計画し、実行に移すためには、現状のエネルギー消費量やCO2排出量を正確に把握することが不可欠です。
しかし、多くの企業でデータ収集・管理体制の不備が投資判断の足かせとなっています。例えば、製品ごとや工程ごとのエネルギー原単位、あるいは使用するエネルギー種別の排出係数が、部門横断で標準化されておらず、正確な排出量を算定できないケースが散見されます。
これでは、どの分野に優先的に投資すべきか、どのような対策が最も費用対効果が高いのかといった戦略的な意思決定が困難になります。
特に、サプライチェーン全体での排出量(スコープ3)の把握は大きな課題です。
多くの部品や素材を外部から調達する自動車産業において、個々のサプライヤーからの排出データを正確かつタイムリーに収集することは容易ではありません。サプライヤーごとに排出量の算定基準やデータ粒度が異なる場合、LCA(ライフサイクルアセスメント)に基づいた製品全体のカーボンフットプリントを正確に評価することができず、サプライチェーンを通じた排出削減の取り組みも進められません。データに基づかない投資判断は、経営資源の浪費に繋がるリスクを孕んでいます。
カーボンニュートラルの推進には、従来の生産技術や環境管理の知識に加え、脱炭素技術、エネルギーマネジメント、データ分析、さらには関連法規や政策動向といった複合的な専門知識を持つ人材が不可欠です。
しかし、現状では「生産技術」と「脱炭素」の両方に精通したハイブリッド人材が社内に不足している企業が多いのが実情です。新しい技術やシステムを導入しようにも、それを理解し、現場で運用・改善できる人材がいなければ、計画倒れに終わってしまいます。
また、自社だけでは解決できない課題に対して、適切な技術やノウハウを持つ社外パートナーを見つけ出し、効果的に連携することも重要です。
しかし、どのようなパートナーが最適なのかを見極める知見が不足していたり、連携のノウハウがなかったりするために、実証実験(PoC)止まりで本格的な導入に至らないケースも少なくありません。カーボンニュートラルという壮大な目標を達成するためには、社内外の知見を結集し、組織的な学習能力を高めていく必要があります。人材育成と外部連携の強化は、この変革期を乗り越えるための鍵となります。
自動車産業におけるカーボンニュートラルの達成は、長期的な視点と段階的な実行計画が不可欠です。ここでは、戦略策定から具体的な実行、そして継続的な改善に至るまでのロードマップを4つのステップで解説します。このロードマップは、企業が直面するであろう課題を乗り越え、着実に目標へ進むための指針となるでしょう。
カーボンニュートラルへの取り組みは、現状のCO2排出量を正確に把握することから始まります。
これは、GHGプロトコルに基づき、Scope1(事業者自らによる直接排出)、Scope2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)、そしてScope3(Scope1、Scope2以外の間接排出、すなわちサプライチェーン全体の排出)のそれぞれを算定・分類することを意味します。
特に自動車産業においては、部品調達から製造、輸送、顧客による使用、廃棄・リサイクルに至るまで、バリューチェーン全体を網羅するScope3の排出量が大きな割合を占めるため、その算定が極めて重要です。
この段階では、エネルギー使用量、購入した製品・サービス、従業員の通勤、輸送・配送など、多岐にわたる活動データを収集する必要があります。算定にあたっては、信頼できる排出係数データベースの活用や、必要に応じて専門コンサルタントの支援を求めることも有効です。正確な排出量データは、削減目標の設定や効果的な対策を講じる上での基礎情報となります。
自社のCO2排出状況を正確に把握した後は、科学的根拠に基づいた具体的な削減目標を設定します。これには、SBT(Science Based Targets)イニシアチブなどが提唱する、パリ協定の目標と整合した目標設定が推奨されます。
長期的なカーボンニュートラル達成目標(例:2050年)に加え、短期・中期(例:2030年)の具体的な数値目標を定めることが重要です。目標は、Scope1・2だけでなく、Scope3についても設定し、バリューチェーン全体での削減を目指す意志を明確にします。
目標達成に向けた進捗を測定し、管理するためには、適切なKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。KPIには、総排出量削減率、エネルギー原単位改善率、再生可能エネルギー導入率、サプライヤーエンゲージメント率などが考えられます。これらのKPIを定期的にモニタリングすることで、計画通りに進んでいるか、対策が効果を上げているかを確認し、必要に応じて軌道修正を行うことができます。
カーボンニュートラルの達成は、特定の部門だけで完結するものではなく、全社的な取り組みと部門横断での連携が不可欠です。経営層の強力なコミットメントのもと、サステナビリティ担当部門だけでなく、製造、調達、開発、営業、人事など、関連する全部門が参画する推進体制を構築します。各部門の役割と責任を明確にし、定期的な情報共有や連携会議を通じて、目標達成に向けた一体感を醸成します。
さらに重要なのは、従業員一人ひとりの意識改革と行動変容です。カーボンニュートラルが企業戦略の根幹であることを周知徹底し、省エネ活動の奨励、環境配慮型製品開発へのインセンティブ、サプライヤーとの協働に向けた研修などを実施します。トップダウンの指示だけでなく、ボトムアップの提案や改善活動が活発に行われるような企業文化を育むことが、持続的な取り組みの鍵となります。
カーボンニュートラルへの道筋は一直線ではなく、技術革新、市場環境の変化、政策動向など、様々な外部要因の影響を受けます。
そのため、一度策定した戦略や計画に固執するのではなく、定期的な進捗管理と柔軟な戦略の見直しが不可欠です。具体的には、Plan(計画)- Do(実行)- Check(評価)- Act(改善)のPDCAサイクルを確立し、継続的に運用していくことが求められます。
最低でも年次で目標達成度やKPIの進捗を評価し、その結果を経営層に報告するとともに、外部にも情報開示(サステナビリティレポートなど)を行います。評価結果に基づき、当初の計画が現実的であったか、より効果的な削減策はないか、新たな技術や制度を活用できないかなどを検討し、必要に応じて戦略や目標、行動計画を更新します。この継続的な改善プロセスこそが、長期的なカーボンニュートラル達成を確実なものにします。
以下では、自動車業界における環境省のモデル事業をご紹介します。
自動車部品を始めとする金属プレス加工メーカー「協発工業」の事例です。工法の開発や金型設計・二次加工まで一貫対応しています。
同社は2030年を目処にScope1・2のCO2排出量を50%削減(2018年度比)という目標を掲げています。その目標を達成するために各種取り組みを進めていますが、より強く推進することを目的にモデル事業に応募しました。
協発工業の二酸化炭素排出量は、電力起源が大部分を占めていました。特に多いのはコンプレッサーやプレス機などの部品製造に使用する設備で、工場を統合して間もなかったため、削減ポテンシャルが大きいと考えられました。
協発工業では、2018年度比で二酸化炭素排出量を50%減らすという目標を設定。これは温室効果ガスによる温度上昇を1.5度に抑える水準に合致しています。
協発工業では、カーボンニュートラルに向けて以下の取り組みを進めています。
同社では、各種取り組みを推進することで2030年に二酸化炭素排出量50%削減を目指しています。
参照元:【PDF】環境省公式HP(https://www.env.go.jp/content/000114657.pdf)
本メディア監修企業である「豊国エコソリューションズ」のコンサル事例をご紹介します。
自動車部品製造を手がけるA社の事例です。同社は、自動車業界内でサプライチェーンにおける二酸化炭素排出量算定の動きがある、と見聞きした程度の認識しかありませんでした。自社にとって、カーボンニュートラルはまだ先と考えていたそうです。
一方、自動車メーカーから二酸化炭素排出量や今後の削減計画を提出する向きがあったため、自社でも二酸化炭素排出量の算定を始めることに。しかし、データ収集にどの程度の工数がかかるのか把握できない問題を抱えていました。
そこで豊国エコソリューションズでは、以下の内容を提案しました。
二酸化炭素排出量の算定方法を中心にコンサルを実施しました。
コンサル後、A社はサプライチェーンの二酸化炭素排出量の算定に必要な情報・工数が理解できたそうです。また、今後業界ルールが策定された場合でも、必要な準備をイメージできるようになったとしています。さらに設備投資のアドバイスももらい、数件の補助金で採択を受けることにも成功しました。
サプライチェーンの二酸化炭素排出量を算定したことで、脱炭素の取り組みが選考していると取引先から評価されるように。以前は取引先から情報を受け取る受け身の状態でしたが、今後は積極的に情報を発信し、営業で活かしていきたいとしています。
世界各国の自動車メーカーおよび政府は、カーボンニュートラル達成に向けて急速に舵を切っています。ここでは、アメリカ、中国、ドイツ(EU)の市場動向と主要メーカーの戦略を概観し、それらを踏まえた日本国内メーカーの先進事例と、私たちが学ぶべきベンチマークポイントを考察します。
米国では、バイデン政権下で気候変動対策が加速し、自動車産業の電動化が力強く推進されています。ゼネラル・モーターズ(GM)は2040年までに製品と事業活動のカーボンニュートラル達成を宣言し、2035年までに新発売の乗用車からの排出をゼロにする方針です。
このEVシフトのため、GMは2025年までに350億ドル規模の投資を計画しています。フォードも2050年までのグローバルカーボンニュートラルを掲げ、2030年までに世界販売の40~50%をEVとする計画です。ただし、主要市場である欧州では、当初2030年としていた乗用車の完全EV化計画について、2024年時点ではEV普及ペースを踏まえ、2030年以降も一部ハイブリッド車を併売する方針に軌道修正する動きも見られます。EV専業のテスラは、製造拠点での再生可能エネルギー活用やサプライチェーンの脱炭素化にも先進的に取り組んでおり、依然として米国・世界のEV市場をリードしていますが、中国のBYDなど他社の急成長によりグローバル市場での競争は激化しています。
これらの動きを強力に後押ししているのが、2022年に成立したインフレ抑制法(IRA)です。IRAは、EV購入者への税額控除(最大7,500ドル)や、米国内でのバッテリー生産・EV組み立てに対する大規模な投資減税を盛り込み、EVシフトと国内サプライチェーン強化を促しています。この税額控除は2032年末までの措置で、北米で最終組立てされた一定条件(購入者の所得制限、車両価格上限、バッテリーの部品・鉱物の原産地要件など)を満たすEVに適用されます。環境保護局(EPA)による厳格な排出基準や、カリフォルニア州をはじめとするZEV規制も、メーカーに電動化を迫る大きな要因となっています。アメリカ市場は、政策と企業の戦略的転換が一体となり、カーボンニュートラルへの道筋を形成しつつあります。
参照元:https://www.energy.gov/energysaver/new-and-used-clean-vehicle-tax-credits
中国は世界最大の自動車市場であり、新エネルギー車(NEV:EV、PHEV、FCV)の普及において世界をリードしています。政府は「2030年炭素排出ピークアウト、2060年カーボンニュートラル」という国家目標を掲げ、自動車産業はその達成に向けた重要分野と位置づけられています。
中国は2025年に新車販売の20%をNEVとする目標を掲げていましたが、実際には2022年時点でNEV比率が約24%に達し目標を前倒しで達成、2023年には新車販売に占めるNEVの比率が35%前後に達するなど、その勢いは目覚ましいものがあります。国によるEV購入補助金は2022年末で終了しましたが、代わりに2024~2025年はNEV購入税免除(最大3万元)、2026~2027年はその半額の減税措置が講じられています。業界ロードマップでは2035年に新車販売の50%をNEVとする目標が示されていますが、近年の普及加速から、より早期の達成や政府による目標の上方修正も検討される可能性があります。
この背景には、政府による強力な産業政策があります。「デュアルクレジット政策」により自動車メーカーに一定割合のNEV生産・販売を義務付けています。
BYDのような新興メーカーは、2022年にガソリン車の生産を終了しNEV専業へと移行、2023年には中国国内の乗用車販売台数でフォルクスワーゲンを抜いてトップブランドとなるなど、大胆な戦略で市場を席巻しています。BYDはプラグインハイブリッドを含むNEV販売で世界首位級となっており、深圳市の本社工場を「ゼロ炭素排出工業団地」として国際認証を取得するなど、製造工程での脱炭素化にも注力しています。CATLをはじめとするバッテリーメーカーもサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル目標を掲げるなど、産業全体での脱炭素化が急速に進展しています。ただし、中国の自動車大手各社もカーボンニュートラル方針を掲げてはいますが、吉利汽車グループ(2045年目標)など一部を除き、具体的な目標年や内燃エンジン車のフェーズアウト計画が不明確なケースも見られます。
欧州連合(EU)は、気候変動対策として2030年までに温室効果ガス排出を1990年比で55%削減する目標(「Fit for 55」パッケージの一部)を掲げています。この一環として、2035年までに新車の乗用車と小型商用車のCO2排出量を100%削減する(実質的な内燃機関車新車販売禁止、2030年に2021年比で55%削減が中間目標)という野心的な目標を法制化しました。これにより新車販売は実質的にゼロエミッション車のみとなりますが、合成燃料(e-fuel)のみを使用する車種については2035年以降も登録が認められる例外規定が設けられています。これを受け、ドイツの主要自動車メーカーは包括的なカーボンニュートラル戦略を推進しています。
フォルクスワーゲングループは2050年までの企業ネットゼロ(サプライチェーン含む)を掲げ、電動化の加速、工場での再エネ100%化(欧米)、バッテリーリサイクル体制の確立などを進めており、VWブランドでは2030年に欧州販売の80%以上をEVとする新目標を設定しています。BMWグループも2050年までのバリューチェーン全体での気候中立をコミットし、2030年までに自動車1台あたりのライフサイクルCO2排出量を2019年比で40%削減する計画です。また、2030年にグローバル販売の半数以上をBEVとすることを目標とし、特に循環経済(サーキュラー・エコノミー)を重視し、再生素材の利用率向上やサプライヤーに対するCO2削減目標管理を徹底しています。メルセデス・ベンツは「Ambition 2039」戦略のもと、2039年までに新車ラインナップをライフサイクル含めてCO2ニュートラル化する目標を掲げ、2022年には自社の全乗用車工場でカーボンニュートラル生産(生産電力の再エネ化など)を達成しました。各社とも電動化だけでなく、製造工程、サプライチェーン、リサイクルに至るまで、LCA視点での包括的な取り組みを強化しているのが特徴です。ドイツ政府は2030年までに国内で1500万台の電気自動車を普及させる目標を掲げていますが、足元の販売ペースはその達成に課題を残しています。
参照元:https://www.volkswagen-newsroom.com/en/e-mobility-and-sustainability-4726
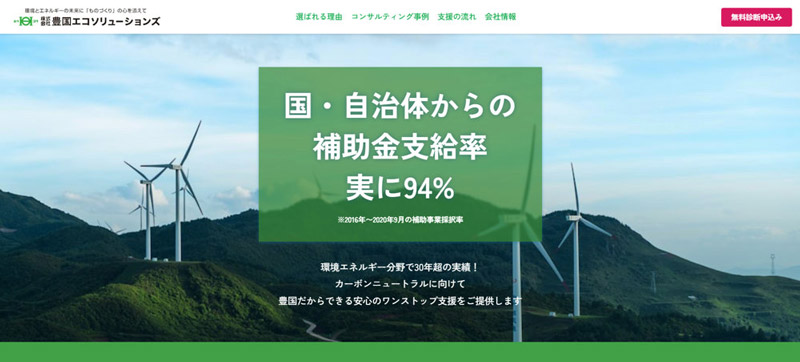
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。