このメディアは、株式会社豊国エコソリューションズの監修・取材協力のもとZenken株式会社が制作・運用しています。
工場におけるCO2削減は、環境対応を超えて経営そのものの質を高める取り組みです。
エネルギー価格の変動やサプライチェーンからの要請に応えつつ、コストと排出の両面で成果を出すには、段階的かつ全体最適の視点が欠かせません。まずは既存設備の見直しから着手し、続いて設備更新、そして運用の高度化へと進めることで、継続的に効果を積み上げられます。
LEDや見える化を終えた工場でも、まだ「見えない無駄」は残っています。
圧縮空気の微小な漏れをAI画像解析やセンサーで素早く特定し、修繕の優先順位まで示すアプローチは、停止を最小化しながら改善を進められるのが利点です。
断熱については、スペース制約で従来施工が難しかった箇所に、薄型で高性能な断熱材を限定的に適用することで、熱ロスの集中的な抑制が期待できます。
さらに、電力の使い方そのものに目を向け、負荷変動に合わせて無効電力を最適補償することで、基本料金の構造的な改善につながります。小さな投資でも、対象を絞って効果の大きい箇所から手を付けることが肝心です。
初期費用は一定規模になりますが、短期間での回収が見込める技術が実用段階にあります。
たとえば、産業用ヒートポンプは少ない電力で高温の熱を生み出す装置で、従来の熱源と比べて効率的な熱供給を実現します。
工場全体を仮想空間に再現するデジタルツイン(工場をコンピューター内に双子として再現する技術)は、24時間の最適運転探索や計画段階の検証により、無理・無駄・ムラを減らす好循環を作ります。
送風や曝気に用いる機器では、摩擦損失を極小化する方式への転換により、動力と騒音の双方で改善が進むでしょう。
さらに、有機ランキンサイクル(ORC:Organic Rankine Cycle。低沸点の媒体を使って比較的低温の熱から発電する技術)により、これまで捨てていた熱を電力に変える道も開けます。
いずれも、単体の効率向上に留まらず、保全・騒音・運転の安定性といった副次的な価値を同時にもたらす点が経営上のメリットです。
設備投資に先立ち、運用そのものを賢くするだけでも削減は進みます。
需要の変動をAIで予測し、段取りや生産スケジュールを平準化すれば、ピーク抑制と稼働率の両立が図れます。
仮想センサー(既存データからAIが温度・圧力・流量などを推定する技術)を使えば、物理センサーの追加なしで最適制御の解像度を上げられます。電力需給が逼迫するタイミングで協調的に負荷を調整する仕組みへの参加は、報酬と省エネを同時に得る選択肢です。
さらに、工程間で熱を段階的に回す「カスケード利用」により、工場全体の熱の使い道を組み替えると、単独の設備改善では得にくい全体最適に近づきます。
工場の形は業種ごとに異なり、最も効く打ち手も変わります。プロセスの本質を押さえ、現場の制約に合わせて優先順位を付けることが、成果を早める近道です。
熱を多用する食品工場では、熱の作り方と使い方の両輪を磨くことが効果的です。過熱水蒸気のように加熱そのものを刷新する方式は、工程の時間短縮とエネルギー使用の圧縮を同時にねらえます。
乾燥では、内部から効率よく加熱しつつ除湿を賢く組み合わせることで、品質と省エネのバランスが取りやすくなります。副産物や廃棄物由来のバイオガスを高度利用し、電力と熱を併給する構成は、原料の循環とコスト耐性の強化に寄与します。
さらに、相変化材料(PCM)による蓄熱を組み込めば、時間軸での熱の使い道も最適化できます。
エネルギー負荷の大きい塗装や熱処理では、まず塗装の当たり前を見直します。AIビジョンで対象物の形状を把握し、塗布と乾燥を無駄なく行う工夫は、材料とエネルギーの双方に効いてきます。
燃焼系では、水素の段階的な混焼からの転換を進めることで、既存設備を生かしながら脱炭素化の道筋を描けます。
人とロボットの協調配置やライン全体の動線最適化は、サイクルタイムと電力の両方を抑える実務的な一手です。
サプライチェーンで工程情報を共有し、バッチ処理を賢く組むと、工場の外側まで含めたエネルギー最適化が見えてきます。
化学工場では、反応・分離・制御を三位一体で設計し直すことが鍵です。マイクロリアクター(微細な流路で反応を行い、熱・物質移動を高める技術)により、反応段階のエネルギー密度と安全性を両立できます。
分離では、蒸留の代替として膜分離を取り入れると、熱の投入そのものを減らせます。触媒の革新として、プラズマ触媒により温和な条件での合成に挑むアプローチは、将来の大幅な削減ポテンシャルを示します。
さらに、AIによる自律運転を導入すれば、変動の大きい現場でも最適点を継続的に追従できます。
機械加工では、工作機械の「止め方」と圧縮空気の「使い方」が成果を分けます。待機時の主軸やサーボの賢い停止、IoTによる稼働監視は、即効性のある取り組みです。
圧縮空気は、漏れの修繕、配管径の見直し、台数制御の適用といった基本を丁寧に積み上げるほど、電力の基礎体力が向上します。
日中の需要に合わせて屋根上の太陽光を組み合わせ、必要に応じて蓄電を加えれば、外部環境に左右されにくい電源構成を作れます。
再生可能エネルギーは、環境価値の確保だけでなく、価格変動への耐性を高める実装でもあります。
工場の設備構成や屋根面積、熱の需要特性に合わせて選択肢を組み合わせることで、投資の確度が上がります。
屋根置き型の自家消費は、発電した電力をそのまま使えるため、長期の電力コストを安定させやすい方式です。設備を第三者が設置・保有し、工場が電力を購入するPPA(電力購入契約)を用いれば、初期投資の負担を抑えつつ、稼働初日からの効果を取り込みやすくなります。契約満了後の取り扱いも含め、全体の費用対効果を俯瞰して検討すると良いでしょう。
ORC(有機ランキンサイクル)は、比較的低温の排熱からでも発電を可能にする技術です。ボイラーや焼却炉、プロセスの冷却水など、多様な熱源に対応できる柔軟性があり、工場の系統に大きな負荷をかけずに電力を取り出せます。
適用温度帯や熱量の把握、既存配管との取り合いを事前に整理することで、導入後の運転が安定します。
木質チップやPKS(パーム椰子殻)などの地域資源を燃料とするバイオマスボイラーは、カーボンニュートラルな熱源として有力です。要点は燃料の安定供給と品質管理にあります。水分率が高いと効率が下がるため、貯蔵・乾燥・異物除去といった運用上の基本を徹底することが、日々の安定運転と保全コストの抑制につながります。
短期の「効く施策」と中長期の「構造改革」を分け、順序よく重ねることで、投資と成果の見通しがクリアになります。段階を区切って計画すること自体が、社内の意思決定を加速します。
最初は全体像の把握から始めます。デジタルツインで仮想的に改善案を試し、効果の見込みを確認すれば、実機への反映で迷いが減ります。AIによるエネルギー診断は、膨大な運転データから人の目が見落としがちな非効率を抽出し、改善の着地点を具体化します。さらに、ブロックチェーンでエネルギー使用量を証跡化すれば、環境対応の取り組みを対外的に説明しやすくなります。
次に、設備面の更新と工場外の連携に踏み込みます。近隣工場と熱や蒸気、電力を融通する仕組みは、一社では得にくいスケールメリットをもたらします。太陽光の余剰電力を電気分解で水素に変え、必要な時に使う構成は、電力の時間シフトと燃料の多用途化を同時に実現します。また、量子コンピューターのクラウドサービスを活用すれば、複雑な組み合わせ最適化を短時間で検討でき、工程や物流の刷新を後押しします。
最終段階では、工場全体の設計思想をアップデートします。大気からCO2を回収して素材として活用する取り組みは、排出の最終バランスを大きく変えます。微生物や酵素を用いて常温常圧で製造するバイオプロセスは、原料転換とエネルギー削減を一挙に進めます。気象や電力価格、生産計画をAIが統合し、ほぼ自律的に最適運転を続ける工場像は、稼働と省エネのトレードオフを乗り越える有力な選択肢です。
制度と専門家を早期に巻き込むほど、投資の負担とリスクは軽くなります。公的支援の条件や時期、社内の準備状況をそろえ、採択から実装までの道筋を逆算しておきましょう。
工場の脱炭素化には、設備費の補助や税制優遇が用意されています。工場全体や主要システムで一定以上の削減を条件とする支援や、中小企業向けの無料診断と一体化した枠組み、認定設備への税額控除・特別償却など、使い分けの幅が広いのが特徴です。応募時期や採択の要件を早めに確認し、事業計画と設備仕様を制度の要件に沿って整理しておくと、審査の通過率が高まります。
省エネルギーセンター等の無料診断は、工場特性に合った改善の打ち手を抽出するのに有効です。外部のエネルギー管理士をスポットで活用すれば、現行の運転データから実装可能な提案まで一気通貫で整理できます。金融機関の環境・エネルギー向けメニューを併用すれば、投資判断の裏付けと資金の手当ても同時に進められます。
ESCO(省エネ改修の設計・施工・維持管理を一括し、削減分から費用を賄う仕組み)を活用すれば、初期投資の負担や実現リスクを抑えられます。設備メーカーとの共同開発は、現場に最適化された技術を素早く実装する近道です。工業団地単位でのエネルギー融通や地域新電力、廃熱の地域供給といった地域プロジェクトに参画すれば、単独では届かない規模の効果を獲得できます。
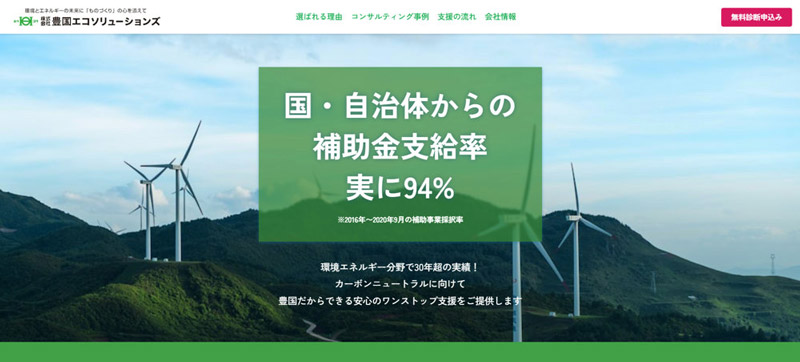
引用元:豊国エコソリューションズ公式サイト(https://carbonneutral-hokoku.lp-essence.com/)
豊国エコソリューションズは、環境・エネルギー領域におけるソリューションを提案しているコンサルティング会社です。補助金・助成金を活用したコンサルティングの豊富な採択実績をはじめ、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)や排出権取引に関するサービスも提供しています。
有資格者数も多く、専門的かつ多角的なサポートを受けられるのも特徴。カーボンニュートラル分野での実績が豊富で、顧客のニーズを踏まえた提案を行っています。
豊国エコソリューションズは、省エネに関する補助金を活用した事業において、高い採択率・採択数の実績を有しています。補助事業の採択率は、2016年〜2020年9月の実績で94%を実現。提案した事業のほとんどが採択されています。一方、採択数も2011年〜2020年9月の累計で563件を数えるなど、豊富な実績を有しています。
※設備更新や補助金活用、再エネ導入検討、運用改善、SBT認証取得、製品・サービスのLCA実施などについて簡易的なアドバイスを行っています。